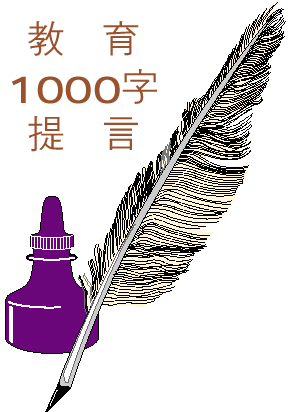|
星宮 望=文
text by Nozomu Hosimiya
私の友人、特に大学時代の友人について、学生時代と社会人になって30年以上経ってからの比較をすると、面白いことに気がつきました。学生時代にすごく頭が切れた(勉強ができた)友人が、その後どうしてかあまり重要なポストについていないことがあります。その逆に、学生時代にそれほど目立つような成績ではなかった友人が、重要なポストについていることもあります。社会に出てからのそれぞれの活動の場には種々の環境・条件に違いがあって、簡単に結論を出すことはできないと思いますが、それでも一つの共通点があることに気がつきました。
前者のグループの友人には、自分のことしか考えない傾向があるように思います。その逆に、後者のグループの友人には、世話役の重要性を若い時から自覚していた人が多かったように思います。例えば、会社で係長、課長、部長と昇進するにつれて、より多くの人の世話をすることになります。責任を持つようになってから気がついても、遅いのです。
学生時代から友人と上手にコミュニケーションを行って、個々の人の希望や主張をまとめたり、違った意見の調整をしたりするコツを身に付けておくことが、重要であることを強調したいと思います。このことは、昔から「情けは人の為ならず(なさけを人にかけておけば、めぐりめぐって自分によい報いが来る〔広辞苑〕)」と言われていることとも合致します。
東北大学の入学試験の中のAO入試の一部では、高校時代に生徒会や部活動で活躍し、かつ成績の良い人を優先しているのも、この点を考慮しているからと思います。
工学部電子工学科の私の研究室では、新しく研究室に来た学生と先輩の学生とがペアになって、コーヒー係、ラーメン係、スポーツ係(駅伝大会、テニス大会、野球大会)、コンパ係(外国人研究者の歓送迎会なども含む)、イベント係(芋煮会など)・・・などの各種の世話役を必ず経験し、その後でゼミナールの世話係などへ進むことにしております。このシステムは私が助教授であった30年くらい前から実施しておりますが、多くの卒業生が社会人になって活躍してくれている、1つのカリキュラム外教育になっているように思います。
平成12年12月に中央教育審議会から「新しい時代における教養教育の在り方について」という審議のまとめが発表され、カリキュラム外教育の重要性も指摘されております。クラシックな意味の教養だけでなく、若者が前向きに自信をもって社会で活躍できるような、素地をそなえる手助けをすることも一つの教養教育ではないでしょうか。
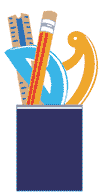
|